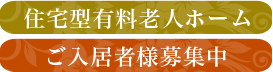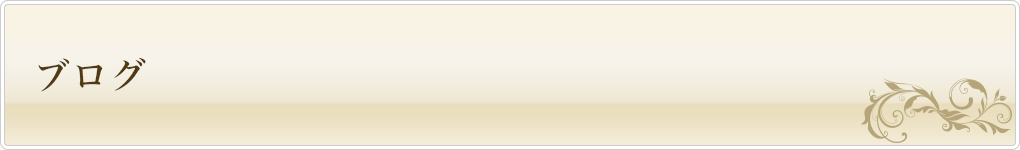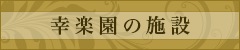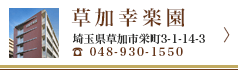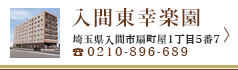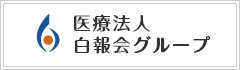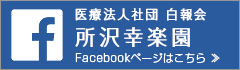お内裏様とお雛様〜♪それはみんなだ雛祭り
本日、3月3日はみなさまがご存じ【ひな祭り】です。

ですが、ひな祭りは日本人の7割以上が本当はどんな意味がある行事かは知らないようです。(私を含め)
そんな物知り3割のハナタカさんたちは再確認の意味でも読んでいただければ幸いです。

それでは6つの真実を発表していきます。
①『うれしいひなまつり』の歌詞に間違いがあった
あかりをつけましょぼんぼりに〜♪と続きますが二番の『お内裏様とお雛様〜』は実は間違い
実はお内裏様というのは並んでいる最上段2人の総称であり、お雛様はひな人形すべてを指します。
そのため、『お殿様とお姫様』になります。
次に、三番の『赤いお顔の右大臣』は正式な配置だと逆になるため『赤いお顔の左大臣』となります。

②ひな祭りは女の子(子供)の行事ではない
なんとなく、小さい頃におこなう(こいのぼり然り)行事のイメージがありますが
「ひな祭りの歴史は平安時代まで遡ります。『上巳の節句』といって、3月の始めの巳の日に、無病息災や五穀豊穣を神様にお供えをして感謝していました。また、紙の人形を身体になでつけることで災厄を人形に移して川に流していました」
それが元々の原型であり
人形を飾ってお祝いをする『祭り(フェス)』の意味合いを持つようになったのは、江戸時代以降だそうで。

話が少しそれましたが、本来の意味は
神様に『将来、幸せな結婚ができますように』とお供えをしてお願いすることとなるため、未婚である限りは永続できるイベントですね。
③雛人形は結婚式の様子を表している

雛人形の飾りの中には、鏡台や針箱、茶道具など生活用具らしきものがありますよね?
あれは嫁入り道具の雛形なのだそう。そして、雛人形全体で理想的な結婚式の様子を表しているそうです。
ちなみに雛人形の後ろにある『ぼんぼり』

昔の結婚式は夜9時から11時の間に行われていました。当時は電気がなかったため、ろうそく立てに火を灯して、結婚式をとり行っていた名残だそうです。
④雛人形、それぞれの人形には深い意味がある
お殿様・お姫様
「最上段にいるお殿様とお姫様は、結婚する主役の2人です」
そこはなんとなくわかりますね。
三人官女
「宮中にお仕えする人たちで、結婚式の承認をする役割を担っています。
いわば神社の巫女さんです。3人の中でも、真ん中の女性が一番上位であり、トップとなって取り仕切っている人。
よく見ると眉毛を剃っていて、お歯黒を塗っています。つまり、真ん中の人だけ既婚者なんです!」
五人囃子
「結婚式を盛り上げる役割を担っていますが、実はこの5という数字に意味があります。昔から、両親と子ども3人の5人家族は、バランスがとれた理想的な家族構成だといわれています。」
「魔方陣をご存知ですか? 縦・横・斜めの3マスずつ合計9つのマスに、1から9までの数字を入れていき、どの列の合計も同じになるように並べるというものです。実はこれ、中央に5がこないと成り立たないんです。」

「このようなことから、5という数字を中心に世の中が回っていると考えられ、理想的な家族に恵まれますようにと囃し立てているのが、五人囃子の役割です」
左大臣・右大臣
「婚礼を見守っているガードマンで、弓と矢を持って、敵の侵入を防いでいます」
三人仕丁
「3人それぞれ表情が違うのですが、ここにも意味があります。人生における喜怒哀楽を表現しているのです」
ちなみに、いま紹介した人形の数は、合計15体。15は先程も出てきた魔方陣の一列の合計数からきているのだそうです。
全ては計算されているんですね。
⑤雛人形は子どもに触らせてこそ意味がある
正直この真実は衝撃でした。
汚れちゃうし、繊細な人形なんだから触るな!が当たり前だと思いますよね
昔から、人形を身体になでつけることで、その人の災厄を人形に移すと考えられてきました。つまり、触ってはじめて厄が移るのだそうです。
だから触らせましょう!
⑥雛人形は代々受け継ぐものではない?
雛人形は持ち主の将来の姿。親の雛人形はあくまでもお母さんのものであり、並んでいるお殿様とお姫様はお父さんお母さんの姿になりますよね?
また、厄を移す役割を果たし、将来幸せな結婚ができるようにとお祈りするための物なので、一人一セットが好ましいようです。
現実的な話になると、ひな人形は高価なものなので、そんなときは紙製や陶器など、少し形やサイズの違った雛人形を用意するのもいいと思います。

以上となりますが。すべてわかっていた方はいましたでしょうか?
全て知っていたのなら本当にハナタカさんです。素晴らしいです!
最後に、「早く片付けないとお嫁に行くのが遅れる」これって実は迷信らしい。